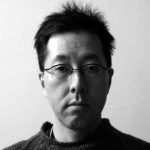
国際免許を取りに,久々に長岡の免許試験場へ行く.
相変わらずの,アクセスの悪さに愕然.というか,こんな厚紙に持参の写真を貼っただけのモノ,しかも書類一枚書くだけで,試験も何のチェックもなく取れるモノを,なぜわざわざあんな遠くまで出向いて2650円も支払わないと手に入れられないのか,はなはだ疑問.
おまけに,申請したら「はい,1時間後に取りに来て下さい.」って,何でこれ作るのにそんなに時間が...
だいたい,2650円って,何の値段だ???
警察が道路交通を管理しているから,自動車免許の管理もしている,というのを何となく当たり前のように思ってきたけれど,何かおかしくないか?自分で許可して,自分で管理して,自分で取り締まって,しかももうずいぶん前から一大巨大産業じゃん.
免許試験場の講師も偉いさんも,駐禁のレッカー屋さんも,パーキングメーターの管理のオジサンも,みんな警察OBかそのお友達でしょう?
とまあ腹は立ったが,その効率の悪い外出のおかげで,「マルチチュード」の上巻をかなり読み進めた.
まだ上巻か?!という声もあるだろうけれど,面白い分だけいろいろ考えてしまって,なかなか進まない.
「哲学書」というより,サバイバル技術のハウツー本.基本となる概念が,丁寧に本文中で説明されている事からも,著者が思考の実験や新しい概念の創出より,その現実世界での実践を主眼にしているのが良く分かる.
ただ,ちょっと気になるのが,思考を展開していく上で重要な鍵となる概念,「生権力」と「生政治的生産」という単語.これらの単語が,もう既に日本語としてこの分野では定着しているものかどうか,勉強不足でわからないけれど,どうもしっくり来ない.文脈からは,著者がこのマルチチュードの中で初めて使った造語のようだが,英語では「biopower」「biopolitical production」となっている.僕はこの「バイオ」が接頭語としてついた英単語を見た時に,極めて素直にそして感覚的にも,「生権力」と「生政治的生産」という単語に訳されている概念に納得がいった.
翻訳者も,きっと悩みに悩んでこの「生」という字を選んだんだろうけれど,何だかなぁ,意味というより文字のイメージや並びのデザイン的に,ずれてるような気がする.
そんなこと気にせず,ちゃっちゃと読み進め,といわれそうだが,言葉の格好良さも大事なのよ.
でもとにかく,久々に興奮する内容.
