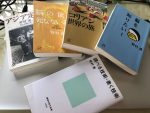Angoulemeからパリに戻り,18日はオフ.
19日の昼にCDG空港を発ってクアラルンプールへ.翌20日朝にKLに着いて,大阪への出発は同日夜の23:55.つまり,ほぼ1日マレーシアに滞在.チケットをお願いした旅行代理店のがんばりで,マレーシアエアラインのトランジットホテルサービスをゲット.朝早く現地に着いて出発が夜中ということは,もしホテルに滞在するとなると,2日間の宿泊になる.それはあんまりなので,ということだと思うのだけれど,朝から同日夜までのホテルが割り当てられるサービスがある.希望者が多いと,必ず泊まれるとは限らないらしいが...
無料のサービスなので,たぶん空港近くの辺鄙なホテルか,KL市内の安宿だろうと予想していたが,実際は予想を超えていた.
空港で乗り込んだシャトルは,走る走る.何度かKL市内まで車で走ったことがあるけれど,どうも道が違う.そのうち高速にのるが,標識が出るたびに,Kuala Lumpurと別方向にあるJohor Bahru方向へ向かう.
1時間ほど走って着いた先はSeremban.KL市内からも,1時間ほどかかるところらしい.ここに,もとHiltonホテルで,今はRoyal Adelphiという名前のホテルがある.
此処の部屋に泊めてもらいました.はい.
部屋は良いです,今回のツアー1ヶ月半で初めて,バスタブのお湯に浸かりました.ぎりぎり間に合った朝ご飯も,お粥やカレーなどマレーシアらしくバラエティーに富んでいてナイス.しかも夕方までゆっくり眠れる.
ただねぇ,ちょっと約束してたんですよ,クアラルンプールの住人と.帰りに寄るから,その時は...
まあ,ちょっとした旅行気分でした(仕事とは違う個人的な旅行).しかもわざわざ,KLから約束していた人が訪ねて来てくれて,見知らぬ町のニョニャ(マレー・中国混血の人)レストランで夕食.なんだか嬉しかったです.
しかし何だってHiltonはあんなところにホテルを建てたのか?マレーシア政府に騙されたのかな?
それで,夜中にKLを発って,翌21日朝に関空到着.
久々に会った娘は,この1ヶ月半の間に段違いに言葉が増えていて,「○○が××したの.」というように助詞を使うようになっていた.今回出発前は,「〜する」とか,「堅い(彼女の意思としては,難しいという意味)」とか,単語でしか話さなかったのに,帰ってきたらちゃんと文章を話している.鸚鵡返しに言葉を模倣しているのではなくて,どうもちゃんと会話が成り立つ.
いやいや,人間の脳は凄いなぁ.
今回,パリのルーブル近くのKEIBUNSYAで,初めて日本語の本を買った.どうも値段が高いのが悔しくて,海外で日本語の書店に行くのは避けてたんだけど,今回は行きの関空で時間がなくて何も本が買えず,活字に飢えてました.ネットで見る日本語と本の活字は別物です.
それで迷いに迷って買ったのが,野村進さんの「脳が知りたい!」.面白かったです.3回も読んじゃいました.決して暇だったからではなく,いろいろインスパイアされました.野村さんの「コリアン世界の旅」も凄く面白かったけれど,一見ぜんぜん畑違いに見える「脳」の話しも,まさにプロフェッショナルなノンフェクションライターといった仕事です.買って良かった.
その中に助詞の話や,LEDにも関係のある色や動きなどの視覚の話も出てきて,色んな興味が広がった.何たって,脳は誰でも持ってるし,他でもない自分のことでもあるんだから.
娘の脳も,色んな能力を獲得しているようです.